

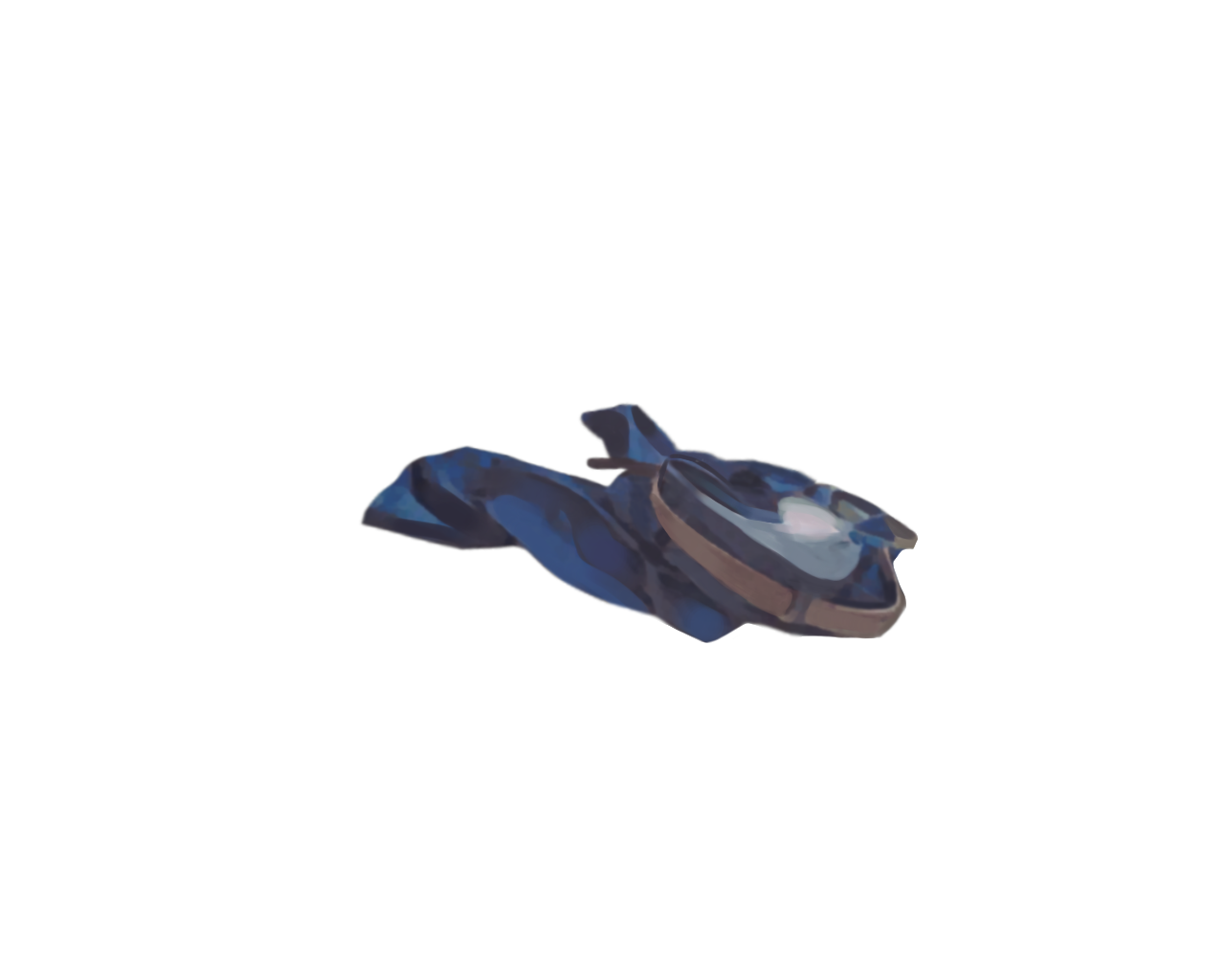

わたしの胸騒ぎを煽るように、雨はよりいっそう激しさを増した。
ベランダの窓から、滲んだ夜街の微光が、暗い部屋の中で
点々と朧きらめいている。
足がすくむ。
滝の裏側に取り残されたようだ。轟音の中でただ孤独だった。
今か今かとこちらをのぞく何か。
浮足立ったが最後、地に足がつくことはないことが分かる。
元の影をなぞるうち、背後の闇は気付けばわたしを囲んでいた。
絶え間ない残響が、徐々にノイズへと変わっていく。
怪訝な面持ちの彼女が影の中でも見えた。
湿った髪先に指が、そっと触れる。
腰に当たった指がこそばゆくて、鳥肌立つのがわかった。
そして、八重歯を覗かせ優しく微笑むのだ。
愛らしいお人形に触れるかのように。
触れた指から、彼女の体温に思いを馳せた。
お互いに細めた瞳の中は、
微光で反射するわたしと朱李で、満たされる。
彼女の柔軟剤が鼻孔をくすぐった。
前髪から垂れた水滴が頬を伝うと、
朱李の親指がわたしの頬を拭う。
呼吸が止まる。
拭ったた部分から枝分かれに、
血の通ったすべてを一瞬のうちに冷やしていく。
心の中を掻きむしられるような激しい焦燥感。
離れていく指を目が追った。
シャワーに入るつもりは感じられない。
あまり身体を冷やしてはいけないだろうに__。
念を押す言葉を飲み込んだ。
リビングルームの電気スイッチに手をかけた朱李は、わたしを見遣
そのまま何もせず、自室へ入っていった。
水面が揺れるリビングは、以前来たときよりも広く感じた。
いくらかの家具や雑貨が片付けられている。
引越し祝いで捨てられずにいた壁絵も、無造作に置かれていた参考書も。
見慣れた物が消えた中で、初めて目にする赤い正体が、
わたしを滝の裏側へ連れ戻す。
棚上に飾られた白い写真立てと、真っ赤な小箱。
喜色満面の朱李と、腰を抱く二つ年上の彼の旅行の思い出の一枚。
彼氏のことは二年も前からよく知っているけど__。
たまらなくなって目を瞑った。
そのとき思い出したのは、幼い頃に犯してしまった罪の記憶。
手のひらの中の、黒い金魚。
滑ったグロテスクな鱗と、レースのように薄いヒレの艶かしさ。
えらと口を小刻みに動かし、出目がこちらを凝視している。
ただの好奇心だった。
水から出した金魚が、どのようにみえるのか。
生きる場所を奪われた生き物が、どうやって息を吸うのか。
七年を生きて、ふとその答えを知りたくなっただけ。
結局、その黒い金魚は死んだ。
ひれを微妙に振り、えら息を吸い心臓を動かしても、
水の中じゃなきゃまるで意味がないのだと知った。
記憶に強く残った記憶の光景は、色褪せることはない。
五感全てに刻まれた死に際は、今なお鮮明に思い出させる。
これはきっと、贖罪
「…そっか、––––––––。」
激しさを増す雨音に、かき消された答え。
届かないのなら、口に出す理由なんてどこにもない。
それでも、欲してしまう。
闇の中で、どうしようもない感情の渦が濁流になって
わたしに息の仕方を教えてくれた。
淡い赤色のギンガムチェック。
可愛らしいパジャマに着替えた朱李。
手には、わたしのために用意した
その場でリネンシャツのボタンを外していくわたしを
朱李は気にもとめず、部屋の電気スイッチに手を伸ばす。
「このままにして」
圧のかかった声で止める。伸ばした手をお腹へと戻した。
シャツ、ズボン、下着、無造作に床に脱ぎ捨て、
ワンピースを受け取り、袖と首を通す。
ふくらはぎを擦れるレース部分が、少々不快だ。
替えの下着も朱李は用意してくれていたけれど、
それには手を付けられず床に置く。
朱李の匂いに包まれる。
真っ白のワンピースは、まるで行衣
床には散らばった抜け殻。
それらをまたいで、わたしはベランダへ向かう。
わたしを呼ぶ朱李の声を背に、ベランダの窓を勢いよく開ける。
絶え間なく雨は降り続け、水平線の向こうまですべてを覆っていた。
ベランダの水溜りに足をつけると、底から冷たさがしみ上がる。
小さな滝飛沫が肌を濡らし、わたしの体温を奪っていった。
目をあけても、そこは闇だとやっと気づく。
最初からわたしはここにいたはずだったのに、光を夢見ていた。
あなたが、わたしに策を尽くさせていた。
手を伸ばせば、朱李と同じ場所に入られるなんて錯覚していたんだ。
朱李の家が今日、片付いていることも
朱李が今日、行きつけの居酒屋に誘わなかったことも
朱李が今日だって、晩酌しなかったことも
朱李が今日なのに、温泉にわたしを連れて行ったことも
朱李が今も、お腹に触れていることも
わかっていたんだ。
それでも目を瞑っていれば、どうにかなるんだって思うしかなかった。
あの小箱を見るまでは。
朱李の苗字は変わってしまうだろうか。
わたしの知っている有楽笠
朱李の血が流れた生命が朱李の体内から産まれ、
そこには家族という形が生まれてしまう。
もうそこに、わたしが立つ隣なんてない。
ただその瞳にわたしだけが映っていればよかったのだ。
親友でいる。届かない片恋はここで終わり。
「 ————————。 」
轟音の中にかき消された声。
ただ呆然とわたしを見つめる朱李を、焼き付ける。
赤茶色の彼女の瞳に光が反射する。
誰よりも幸せになってほしい。
素敵な家庭を築き、大切な人と共に歳をとる。
わたしの知っている朱李なら、大丈夫。
大きく息を吐いた。なぜだかとても高揚している。
待ち遠しさに心が躍っているのか。
手のひらの中で死んでいった黒い金魚は、
同じ水槽の中の赤い金魚に比べて不恰好であった。
ただ一匹、一際目を引く
絹のように繊細な尾鰭をたなびかせ、美しく泳ぐ。
その様は優雅さで溢れ、他を寄せ付けない。
他の三匹であった、黒い金魚の中の、見分けもつかぬその一匹。
それでも、生命が果てるその一瞬、その死に際が、贖罪となり、
酷く聡明に、明瞭に、わたしの中に残り続けた。
命の波紋を感じたとき、何よりも鮮やかであった。美しいとさえおもったから。
あなたの黒い金魚になりたい。
ぼんやり揺れる視界に
わたしを見下ろす僅かな赤色が映った。
もう手を伸ばすことはできない。
朱李に触れてみたかったな—————。